カナムナリス病(尾腐れ病・ヒレ腐れ病・口腐れ病・エラ腐れ病・皮膚病・ネオン病)
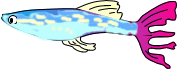 |
特 徴
カラムナリスの細菌感染により発生する病気で、 発病すると進行が早く、伝染性も強いため、注意が必要です。
水カビ病のように見えるが、カラムナリス病は患部に菌糸が見えないので区別が付きます。
発病の個所により尾腐れ病・ヒレ腐れ病・口腐れ病・エラ腐れ病・皮膚病・ネオン病などと呼ばれます。
症 状
初期状態では、菌が増殖している部分に黄白色の付着物が見え、進行すると患部が広がり筋肉部分まで及び、最終的には死にいたります。
●尾腐れ病・ヒレ腐れ病
初期では尾・各ヒレが充血し、色が冴えなくなり、先端部は白っぽくなります。 症状が進むと、ヒレの膜の部分が溶けて条だけ残り、破れ傘状態にり、
更に進行すると、条の部分も溶けてボロボロと崩れ、最終的にはヒレのすべてがなくなってしまうこともあります。
●口腐れ病
口周辺が炎症を起し、赤または黄色っぽくなります。 口の先端部分から組織が黄色・灰白色に変色し、ボロボロと崩れてしまい、口が欠けてしまうこともあります。
●エラ腐れ病
熱帯魚の場合、エラの中の症状に気づくのが困難で進行を見逃しやすいため、手おくれになり死亡しやすい。
初期ではエラやエラ蓋の一部に菌が繁殖し、黄白色の付着物が見えます。
症状が進行するにつれ、菌に冒された部分が広くなり、エラの組織が壊死したり、エラの一部が腐って欠落してしまい、 エラ周辺の組織は痩せ、ゴツゴツした状態になります。
エラの機能が低下するため呼吸困難に陥り、口やエラの開け閉めの速度が速くなり、水面近くで鼻上げしたりします。
疑いのある場合は、エラの内側をよく観察し薄いピンク色や黒ずみが見られたら治療するようにしましょう。
●皮膚病
体表に黄白色の付着物が見えます。ヒレから感染することが多く、それが進行して皮膚に広がる場合が多いです。
進行すると、体表が白くボロボロになり、ウロコが剥がれる。 体を石などに擦り付けたり、狂ったように泳いだり、じっとして動かなかったりする場合もあります。
●ネオン病
ネオンテトラなどの小型の魚が掛かりやすい病気で、体の色が抜けたようになりやがて出血(背ビレのつけ根など)を伴いながら白濁し死んでしまいます。
原 因
飼育水が古くなった。
水質の悪化。
治療方法
飼育水の水1/3程度の換水をおこない、水槽で使用したネットなどは必ず洗浄します。
魚体に傷を見つけたら、塩水浴(0.5%~1%の塩水)で傷がふさがるまで様子をみます。
発病している場合は早めに隔離し、薬浴、塩水浴を行います。比較的塩分に弱いため、1%の塩水浴での治療もできます。
カテゴリ一覧
